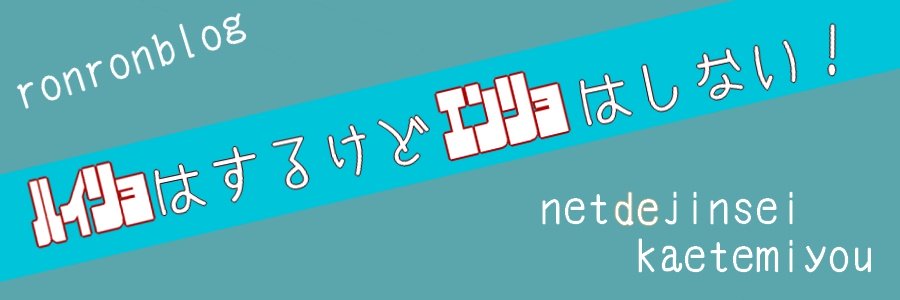寝室は1日の疲れを癒す大切な場所です。
人間の3大欲求の1つでもある【睡眠欲】を満たす場所、とも言えます。
そんな場所が『寝れたらいい』なんて状態では、運がよくならないどころが、運気がドンドン下がってしまいます。
寝室は、風水でみると健康運に大きく関係しているんです。
もので溢れていたり、刺激が強いものをおかず、スッキリした状態を保つように心がけましょう。
本記事では、風水において寝室でやってはいけない6つのことについて紹介しています。
もし、やってはいけない風水に当てはまっていたら、それを避ければいいだけなので、風水コンパスなどの専門道具や難しい知識は一切必要ありません!
あなたの寝室は健康運が上がるお部屋になっているか?
それともあなたの疲れを倍増させてしまっているのか!?
さっそく見ていきましょう!
やってはいけない!6つの運気が下がる風水【リビング編】
風水から見る【寝室】の役割とは
寝ている間、体には様々な事が起きています。
消化や代謝はもしろん、風水の面でいうと【気の循環】が行われているんです。悪い気を消化し、良い気が巡ってくるように整えます。
このサイクルが滞ってしまうと、睡眠の質が落ち、健康や生活に支障をきたします。
風水とうつ病の関係
風水っていうとスピリチュアルな感じが強いですが、その中身を見ていると、運気を上げるためには気の巡りをよくするために通気性をよくしたり、部屋が雑多にならないように物を置き過ぎないなど、今でいう環境学にも似ています。
じつは現代病でもある【うつ病】には風水と関連性があることもわかっているんです。
うつ病の大半は睡眠障害から始まると言われています。
ストレスなどの影響ももちろんありますが、それだけではないはずです。
どうですか、そんな寝室で豊かな睡眠が得られそうですか?
眠ることはできるでしょうが、心身を回復させることは難しいですよね。
そう思うと、うつ病には環境も影響していると思いませんか?
やる気が出ない、何をしてもテンション上がらない、だるい、寝ても疲れが取れない・・・これは空間も大きく関係しているんです。
なので、寝室は『寝れればいい』なんて思わず、寝具や寝室に気を遣ってみてください。
1日24時間のうち3分の1を過ごす場所なのです。
つまりは人生の3分の1を過ごす場所。
質のいい環境で質のいい睡眠を得る。これが大切です。
寝具は暗い色を選ばず、明るくて落ち着いた色、素材も季節に合わせたものに変えていきましょう。
週に一度はお布団を干すか、布団乾燥機でジメジメを吹き飛ばすこともオススメします。
1万円以下だし、布団の乾燥の他に靴も乾かせるのでこの時期重宝します。
今すぐ避けよう!運気が下がる6つの風水【寝室編】

・枕元にぬいぐるみやものがたくさん置いてある
・テレビ・スマホなどの家電製品が多い
・メイク道具が散乱している
・ベッドの下に引き出しがあり、隙間がない
睡眠の障害となる障害物は片付け、枕回りは常にものがない状態にしましょう。
『ホッ』とできる空間づくりを意識していれば、風水的にも運気が上がる部屋になっていきます。
テレビなど大きな電化製品がある場合は、布でカバーするとOK。
風通しをよくし悪い気が流れるように、ベッドは足付きのものをチョイスします。
隙間収納・・・とベッドの下に物を押し込まないようにしましょうね。
【こんな寝室はNG】布団を干していない
日本は湿気大国というのはご存知ですよね?
とくに今の時期は雨が降っていなくても湿度60~70度、雨なんて降った日には90度を超えてしまいます。
布は水を吸うので、寝汗はもちろん、お部屋の空気中の湿気も吸ってしまうんです。
湿気は開運の天敵。
最低でも1週間に一回は布団を干すか、布団乾燥機を使用しましょう。
日の光をたっぷりと吸収したお布団で眠るのは格別ですよ。
【こんな寝室はNG】枕の位置やカバーの色をまったく気にしていない
風水の本場、中国では北枕が吉とされています。
お部屋の構造上、北枕で眠れない場合は枕カバーを寒色カラーにしてみてください。
また、ドアやクローゼットを開けたらすぐ枕がある、という状態はNGです。
ドアのような尖ったものやでっぱりがあると無意識の内に緊張していまい、疲れがとれにくくなるためです。
【こんな寝室はNG】床に直接布団を敷いている
床にはホコリ以外にも悪い気が溜まっています。
そのため、寝具はなるべく足付きの物が望ましい。
どうしてもお布団で寝たい場合は、すのこの敷くか、高さのあるマットを敷いて床から少しでも離れて眠りましょう。
通気性をよくすることで、運気の循環もよくなりますよ。
【こんな寝室はNG】テレビや鏡に寝姿が映る
電化製品があると睡眠の妨げになるので、できるだけ部屋にはおかない方がいい。
また、鏡やテレビの画面に自分が寝ている姿が映っていると、気を吸い取られると言われています。
置かないのが一番ですが、どうしようもない場合はカバーをかけることをオススメします。